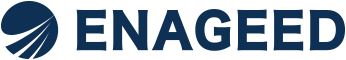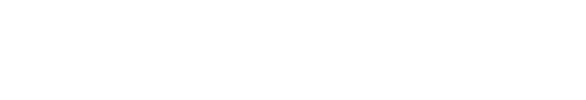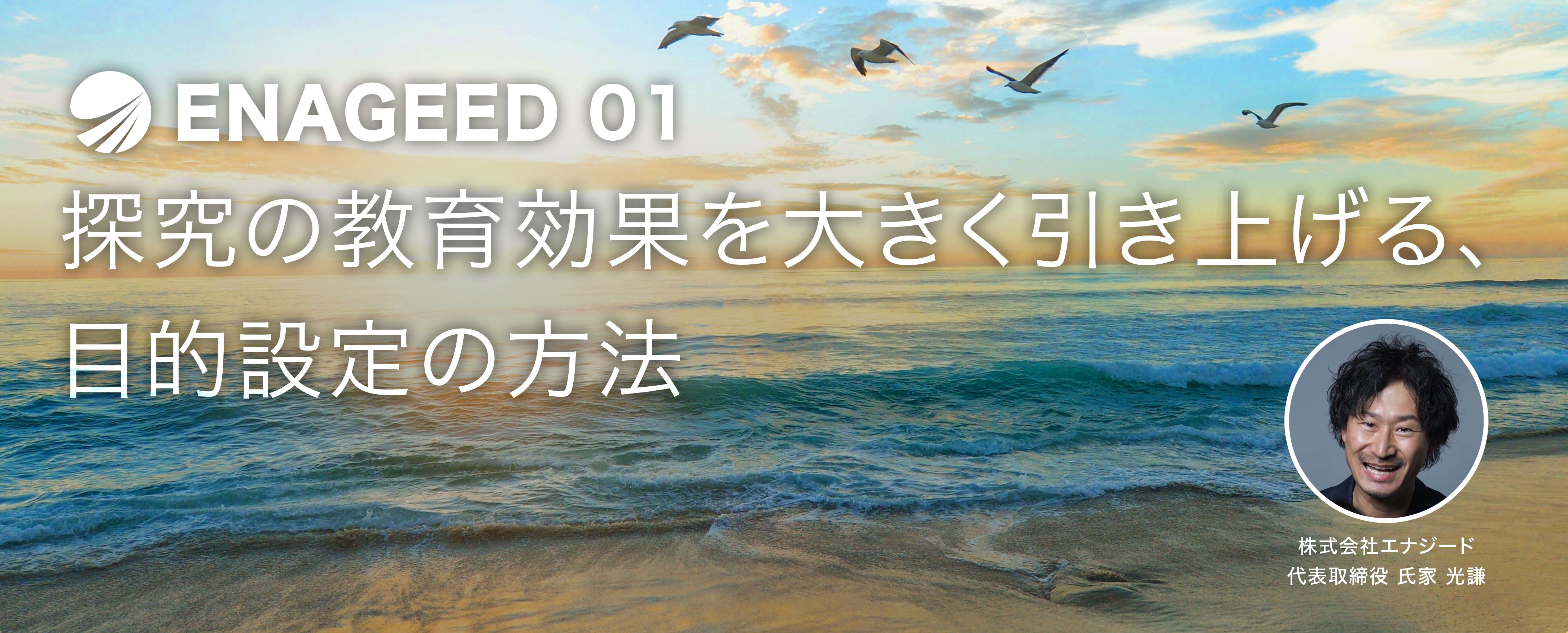
今年も4月に多くの新卒生が就職しました。
この文章を読んでくださっている先生方の中には
今年の新卒生たちを教え子として受け持っていた先生方もいらっしゃるかもしれません。
彼らは社会人研修を受ける経験や
これまで出会わなかった様々な大人と接点を持つ経験を通じて
新しい価値観を得ると同時に、
私たち株式会社エナジードは、中高生向けの教育サービス提供だけではなく
企業様向けに社会人教育の事業を行わせていただいております。
多くの企業様から伺う新卒社会人の傾向として
「自己肯定感の低さ」や「コミュニケーション能力の低さ」、
「受け身のスタンス」などが挙げられます。
もしかすると、先生方も過去に受け持たれていた生徒を思い出し
その傾向に対して納得感があるかもしれません。
それらも含めた若年層世代の傾向に対して、
中央教育審議会は以下の教育方針を打ち出しています。

自分の良さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し
多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、
持続可能な社会の創り手となることができるようにすること
こちらは、中央教育審議会が現代の若手層世代の傾向に対して打ち出している教育方針となります。
普段は固く感じるかもしれないこのような内容が、
実際に接していた生徒の傾向や、社会に出るリアルな瞬間から考えると
重要な課題として感じることができるかもしれません。
日本は様々な国家課題を抱えている中で
この教育方針の打ち出しと共に
以下のような様々な手段を持って解決に向かおうとしています。

・探究教育の実施
・カリキュラムマネジメント
・個別最適な学び・協働的な学び
・アクティブラーニング
・GIGAスクール
・学習指導要領の改定
これら一つ一つは活用・対応することが簡単ではなく、
これまで先生方が培われてきたやり方を大きく変えたり
その背景を保護者や生徒のみなさんに説明しなければいけない
場面もあるかもしれません。
ビジネスでも地域のプロジェクトでも、
何かに取り組む時にその工数が多いほど起こりやすいのが「手段の目的化」です。
「ICTの導入」や「カリキュラムの編成をすること」自体が目的になってしまい、
結果的に生徒の本質的な成長が 生まれなかったというケースを伺うことがあります。
では、このような結果にならないためには、どのようなことが必要なのでしょうか?

「探究学習をすること」や「ICTの導入」
「目の前の生徒のどんな成長を実現する為に、
設計し、その実現に向けて取り組むことをお勧めします。
【問題/今ある、生徒の傾向】→【課題/成長後の姿】
(例)
《問題》自分の考えを言葉にするのが苦手
→《課題》自分の考えを表現できるようになること
《問題》自分で考えずに、言われたことをそのままやる
→《課題》自分で目的を持ち、考えて行動できるようになること
《問題》失敗を恐れる傾向がある
→《課題》挑戦することの意義を理解し、
《問題》改善策ではなく、不平や不満を言ってしまう・・・
→《課題》文句ではなく、改善策を。発案だけではなく、
これらの「問題設計」自体、ベストな正解があるわけではないので
施策を進める中で変更しても良いものですが、
「設計すること」と「それを意識しながら施策を進めること」
普段生徒と接する中で先生が感じる「違和感」。
まずはこれを言葉に落とすことと、
先生方の間でその言葉について合意形成することが、
問題設計につながります。
文科省も先生方も、我々エナジードも、教育の先に目指す姿は
大きく変わらないと感じております。
生徒の目はキラキラしてほしいし、可能性を広げたい。
その先にある、社会の未来を豊かにしたい。
ただ、その過程にあるものが複雑であればあるほど、
手段は目的になり、何のための工程かが見えなくなる瞬間があるかもしれません。
ENAGEEDのサービスを導入頂く際も、ENAGEEDは「手段」です。
導入することで成し遂げる「目的」の設定を先生たちと一緒に考えさせていただいております。
そうすることで活用後の効果は大きく変わると実感しております。

「この先の未来、自分が人生をどう歩んでいくか」の判断基準を、生徒一人ひとりが考え抜くためのテキスト&ムービー。
「これってなんのために勉強するの?」をなくし、意志ある学習を実現する5教科の副教材。