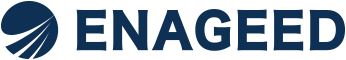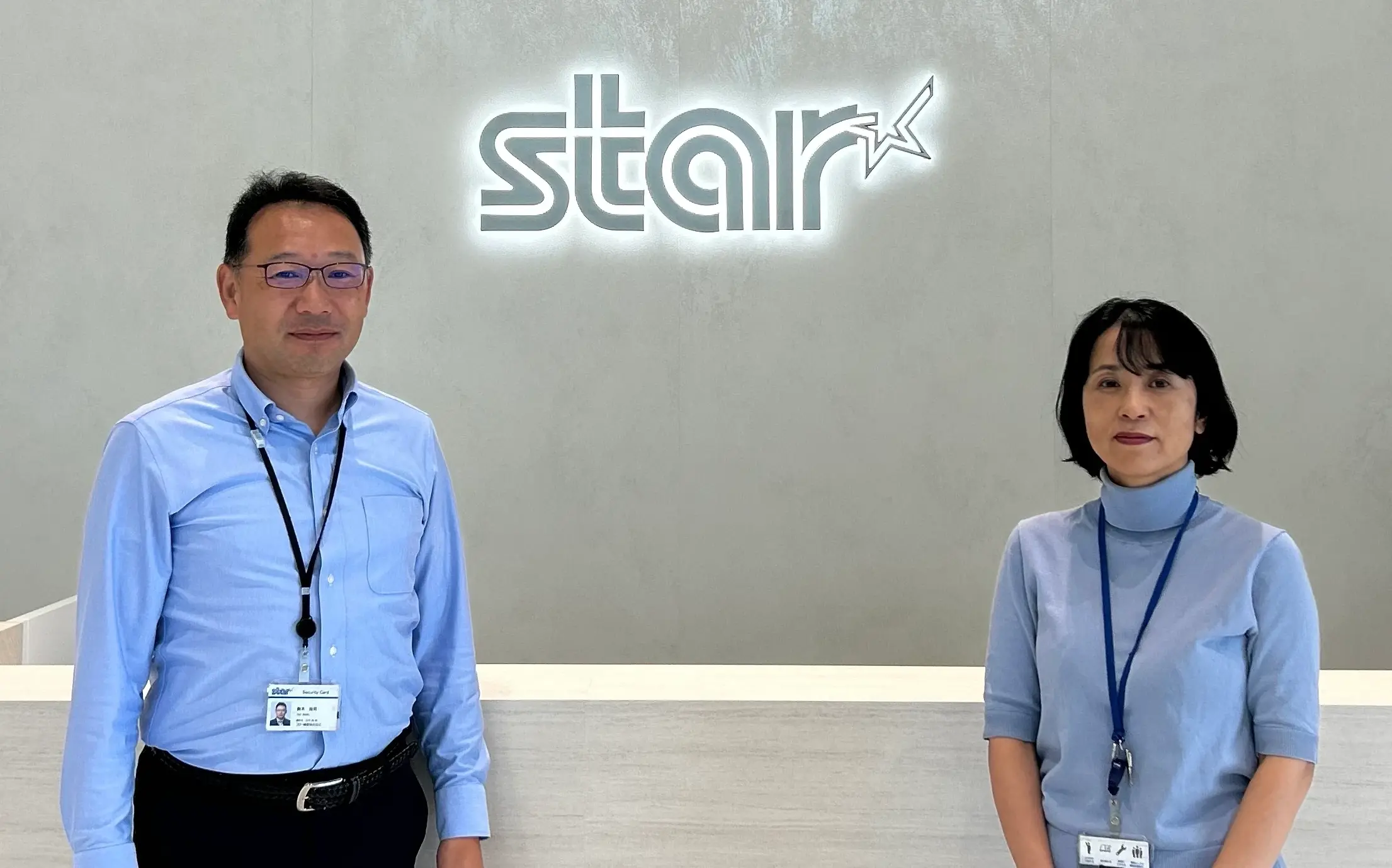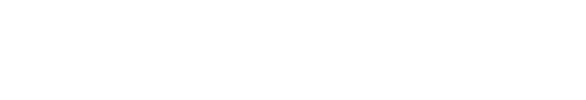挑戦を文化に──オハラが描く「長期ビジョン2035」と人材育成の未来

株式会社オハラは1935年の創業以来、日本初の光学ガラス専業メーカーとして、デジタルカメラや車載カメラ、プロジェクター、半導体露光装置、顕微鏡、内視鏡などの幅広い光学機器向けに、高品質なガラス素材を開発・供給してきました。光学ガラスで培ったナノテクノロジーを活かし、ガラスに熱処理を加えて特性を付与したガラスセラミックスの開発・供給も展開。特に極低膨張特性をもつガラスセラミックスは、人工衛星や大型天体望遠鏡のミラー材に採用されるなど、宇宙・天文分野の最先端領域で高く評価されています。
2035年に創立100周年を迎えるにあたり、「長期ビジョン2035」を掲げる同社。光学ガラス・特殊ガラスを通して新しい価値を提供し社会課題を解決することで、企業価値向上と持続的な成長を目指しています。その実現に向け「世界に通用する人を育てる」企業への進化を推進しており、施策の一環として「オハラアワード」や「チャレンジ目標管理制度」を導入、挑戦を後押しする仕組みづくりを進めています。
今回は、上級執行役員 総務人事センター長 西田様、人事部長 菊池様、人事課長補佐 小島様、さらに研修を受講された荻野様・寺本様・森様に、ENAGEED導入の背景と成果、そして挑戦が息づく組織づくりへの想いを伺いました。
長期ビジョン2035と人材育成の課題
――まず、ENAGEED導入の背景を教えていただけますか?
西田様(上級執行役員 総務人事センター長):
会社として「長期ビジョン2035」を掲げていますが、その実現に不可欠なのは、社員一人ひとりが主体性を発揮し、自ら考え動く文化を根付かせることでした。従来の研修は知識インプットが中心で、行動や意識の変化にまではつながりにくい。そこで「挑戦を促す仕組み」と「挑戦を支える文化」の両輪を整える必要があると考えたのです。

――数ある研修の中で、ENAGEEDを選んでいただいた決め手は何でしょうか?
西田様:
大きなポイントは「社員自身が考えて気づき、行動を変えていける設計」でした。トップダウンの指示ではなく、社員が「自分ごと」として主体的に動くきっかけを与えてくれるプログラムだと感じました。さらに、上司と部下がそれぞれの立場でENAGEEDのプログラムを受講することで、時間差はあっても共通の言語や視点が生まれます。役職を越えて同じテーマに向き合うことが、相互理解を深め、挑戦を後押しする関係性につながると期待しました。
制度と研修を連動させる「挑戦」
――研修設計の段階で工夫された点について、人事部の立場からはどのように感じていらっしゃいますか?
菊池様(人事部長):
人事としての課題は、従来の研修が「やらされ感」で受け止められがちだった点でした。ENAGEEDは社員の思考や価値観から出発するため、自然に前向きに取り組めることが大きな違いです。
さらに、ちょうど「チャレンジ目標管理制度」を導入したタイミングと重なりました。社員が自ら挑戦を設定し、その取り組みを加点評価する制度です。研修で育まれる“挑戦マインド”と制度を連動させることで、文化として定着させられると考えました。
実際に、タスクチームの公募や部門横断の協働など、小さな挑戦が芽生え始めています。研修と制度を掛け合わせることで、「挑戦を後押しする会社」として、社員の自己効力感を支える基盤をつくることを目指しています。

――研修後の定着や制度とのつながりについてはいかがでしょうか。
菊池様:
まだ道半ばですが、受講者のネットワークができ始め、一体感が生まれています。特に「できない」で終わらせず「やってみよう」と前向きに捉える会話が増えました。「挑戦」を加点対象とした評価制度のほか、タスクチームを公募制にするなど、仕組みの面からも挑戦を支援しています。
もちろん課題もあります。部署によっては、挑戦の定義が難しいなどの声もあります。ただ、現場の工夫や小さな取り組みも評価することで、「挑戦は歓迎されるもの」という雰囲気が少しずつ根付き始めていると感じています。
受講者の変化:視野の広がりと「意味づけ」による仕事の面白さ
――ここからは受講者の皆さまに伺います。印象に残った学びや変化を教えてください。
荻野様(研究開発センター):
 「研修では、自分の強みや思考のクセを客観的に振り返るワークがありました。これまで“周囲をサポートするのが自分の役割”と漠然と思っていましたが、分析を通じて『自分は新しい着眼点を見つけることが得意だ』と気づいたんです。環境や役割によって強みの活かし方は変わるし、まだ発揮できていない可能性があると実感できました。
「研修では、自分の強みや思考のクセを客観的に振り返るワークがありました。これまで“周囲をサポートするのが自分の役割”と漠然と思っていましたが、分析を通じて『自分は新しい着眼点を見つけることが得意だ』と気づいたんです。環境や役割によって強みの活かし方は変わるし、まだ発揮できていない可能性があると実感できました。
その後、有志メンバーで新製品のアイデアを形にし、オハラアワードで表彰されました。以前なら“こんな提案をしていいのか”と躊躇していたと思います。でも研修を経て“挑戦は歓迎されるもの”だと背中を押された感覚があり、思い切って取り組めました。結果として会社からも評価を受け、『挑戦してよかった』と実感できた瞬間でした。」
寺本様(事業企画室):
 「研修で学んだ“他者視点”や“上司視点”を仕事に持ち込み、実際に他部署に自分たちの活動を評価してもらいました。結果、業務の意味や貢献度が可視化され、部署間の壁を越える大切さを肌で感じました。グループワークで仲間と喜怒哀楽を共有した経験も大きく、研修後には“ただの同僚”が“相談できる仲間”へと変わりました。信頼関係が生まれると、挑戦への一歩を踏み出す勇気も湧いてくるのだと実感しています。」
「研修で学んだ“他者視点”や“上司視点”を仕事に持ち込み、実際に他部署に自分たちの活動を評価してもらいました。結果、業務の意味や貢献度が可視化され、部署間の壁を越える大切さを肌で感じました。グループワークで仲間と喜怒哀楽を共有した経験も大きく、研修後には“ただの同僚”が“相談できる仲間”へと変わりました。信頼関係が生まれると、挑戦への一歩を踏み出す勇気も湧いてくるのだと実感しています。」
森様(研究開発部):
 「研修で印象に残ったのは“ピラミッドの話”です。目の前の作業も、最上段の“会社としての価値”につながっていると学んでからは、同じ仕事でも捉え方が変わりました。以前は『ただ実験をこなすだけ』と感じていましたが、今は『この試験結果が次の材料開発につながる』と意味付けできるので、自然と前向きになれました。
「研修で印象に残ったのは“ピラミッドの話”です。目の前の作業も、最上段の“会社としての価値”につながっていると学んでからは、同じ仕事でも捉え方が変わりました。以前は『ただ実験をこなすだけ』と感じていましたが、今は『この試験結果が次の材料開発につながる』と意味付けできるので、自然と前向きになれました。
その気づきが行動にもつながり、上司に“こうすればもっと効率的に進められるのでは”と提案するようになりました。これまでなら口にしなかった意見も、自信を持って出せるようになったんです。上司から“好きにやってみろ”と任されたときは驚きましたが、自由度のある環境の中で自分のやり方を試す楽しさを実感しました。今では“仕事を面白がれる”日常に変わっています。」
挑戦が息づく組織文化を全社へ
――最後に、今後の展望をお聞かせください。
西田様:オハラアワードやチャレンジ目標管理制度と組み合わせながら、挑戦を正しく評価する風土をさらに広げていきたいと考えています。ENAGEEDを通じて芽生えた「自分から挑戦する」感覚を、部署や世代を越えて全社に根付かせることが次のステップです。最終的には、社員一人ひとりが自分の可能性を信じて挑戦できる組織文化を確立し、それを通じて企業としての競争力を高めていきたいと思います。
ENAGEED導入をきっかけに、オハラでは「挑戦を評価する制度」と「挑戦を後押しする研修」が連動し、組織文化に変化が芽生え始めています。経営層が掲げる長期ビジョン、人事部が整えた仕組み、そして受講者のリアルな変化が重なり合い、社員の自己効力感と挑戦意欲を育む基盤が形成されつつあります。
「挑戦が息づく組織文化」は、オハラが未来に向けて歩みを進める大きな推進力となっていくでしょう。
最後に
オハラは「挑戦」をキーワードに、人材育成と制度改革を結びつけ、組織文化そのものを変革しようとしています。ENAGEEDの研修は、その変革の土台を支える存在となり、社員一人ひとりの挑戦が組織の未来を形づくる力へとつながっています。
――本日は貴重なお話をありがとうございました!
エナジードは、オハラ様とともに「挑戦が息づく組織づくり」をこれからも全力でご支援してまいります。